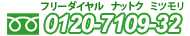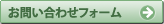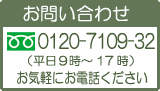大切なお寺とご家族を将来に亘って守る証としての保険を 保険情報サービス株式会社
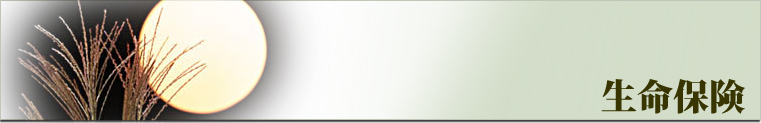
宗教法人の保険加入の目的
寺院において保険に加入する目的は、「事業保障資金」、「死亡退職金・弔慰金」、「役員生存退職金」と、大きく別けて3つ考えられます。その他に建物の維持管理として定期的な本堂や庫裡などの「建物改修費」があります。改修工事の借入金の返済がある場合にはその返済資金を用意しておく必要があります。
■事業保障資金
住職が死亡した場合、すぐに寺院葬等の費用が必要となります。また最近は住職に子がいない場合や子がいても子が継がない場合、外部から新しい住職を迎え入れることになり、そのための資金準備が必要となります。その場合、遺族の新しい住居費用や生活費の確保等の準備が別途必要となります。また借入金がある場合は、借入金の返済や職員の当面の給与も必要になる場合も考えられます。生命保険は寺院の「事業保障資金」として、住職が死亡した場合の高額資金準備に役立ちます。
■役員死亡退職金・弔慰金
万が一勇退まで至らず死亡してしまった場合、宗教法人が支払う死亡退職金や弔慰金は、住職の家族の今後の生活資金の確保、相続対策資金として考えられます。また死亡退職金を遺族が受け取る税務上のメリットとして(500万円×法定相続人)が「非課税限度額」になります。さらに個人で加入している生命保険もこの「非課税限度」が適用できます。また別建てで支払う事ができる弔慰金も一定の金額までは非課税になります。弔慰金の非課税と認められている金額は、住職の死亡が活動中であるとき「最終報酬月額の36ヶ月」、それ以外の場合「最終報酬月額の6ヶ月」で、この金額を超えた部分は死亡退職金としてみなされます。生命保険が死亡退職金・弔慰金目的に適している理由は、仮に契約後すぐに死亡したとしても、一連の資金が瞬時に準備できることです。これは保険にしかできない役割です。
■役員生存退職金
住職は声が続く限り、生涯現役であることが当たり前と一般的に思われているだろう。しかし現在では勇退される住職も増えてきているようです。この場合、一般の法人の役員と同じように、宗教法人の代表役員である住職も「退職慰労金」を受け取ることができます。
税法上、退職所得は「退職所得控除」と「分離課税」という大きなメリットがあります。 例えば勤続年数40年の場合には、800万円+70万円×20年=2,200万円が退職所得控除となります。つまり5,000万円を住職の退職金として受け取った場合の個人の課税所得は、(5,000万円−2,200万円)×1/2=1,400万円となります。さらにこの1,400万円の課税所得は、その年の報酬と合算しなくてもよい「分離課税」となります。
【退職所得控除の計算式】
退職所得の金額は以下の計算式により計算され、この金額に税率を乗じ、控除額を考慮することにより退職金にかかる税金が計算されます。
退職所得金額=(退職金−退職所得控除)×1/2
退職所得控除額は勤続年数に応じて以下のように定められています。
●勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数
(1年未満は切り上げ。勤続年数2年以下は80万円)
●勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数−20年)
■役員退職金規定
勇退資金や死亡退職金の準備と同時に寺院として規定の整備も必要となります。理由は税法上の理由とトラブル防止の2つがあります。まず税法上の理由としては、勇退時の退職金は大きな金額になりますが、宗教法人として何のルールもなく住職に対してお金を支払うとなると、税務署から根拠のない住職への支払いと認定される可能性が出てきます。退職金として否認されてしまうと、税制面での退職金のメリットもなくなってしまいます。
次にトラブル防止としてですが、役員退職金の支払いは寺院において高額な財産の処分にあたるため、檀家からの承認と責任役員会での決議が必要不可欠です。前もって住職の退職金の支払い額を決めておき、実際の支払いの段階でいくら支払うかを再度、檀家総代への説明と責任役員会の承認を取り付けておくことが好ましいでしょう。
退職金の支払い基準は自由ですが、税務署が認めている一定の計算基準の基づく過大な退職金とみなされない妥当性のある金額であれば概ね問題がないようです。計算根拠は「最終報酬月額」×「在任年数」×「功績倍率」が一般的で、住職の場合、功績倍率は1〜3倍が用いられています。
役員退職金規定を作成することは寺院側だけではなく、檀家や税務署などの周囲の了解を取り付ける重要な契約書を作り上げるということです。そしてこの金額設定と規定は退職金を確実に受け取るための、重要なポイントになることになります。
H23.7月13日現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。 税務上の取扱が税制改正などで変更になることがありますのでご注意下さい。 また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談下さい。
【お寺の生命保険に関するお問い合わせ】
下記フリーダイヤルか、お問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
法人コンサルティング部 伊東(平日9時〜17時)